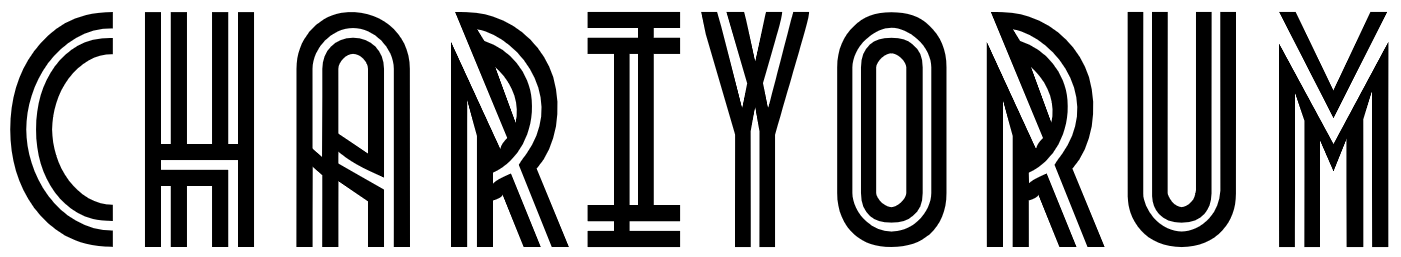最近のレースシーンでは、イギリス男子選手の躍進も目覚ましいですが、女子はオランダが強いです。もっと言うなら、最近だけじゃなくてずっと強くて、どれだけ強いかというと…2018年の例を取れば
- ワールドツアーレースのうち3分の2をオランダ籍の選手もしくはオランダ籍チーム所属選手が優勝
- Annemiek van VleutenとMarianne Vos、Anna van der Breggenの3人がシーズンのポイントランキング争い
- 年間チームランキングの1位と3位を独占(2位のミッチェルトンスコットはほとんどVan Vleutenのおかげ)
- 世界選手権個人TTの表彰台独占(ジュニアも優勝)
- 世界選手権ロードレース優勝(39km独走の圧勝)
マリアンナ・フォスという偉大な選手の名前を一度はきいたことがあるかもしれませんが、彼女だけではないのがオランダという国なのです。「世界選手権より国内選手権のほうがハードだ」とまでいわれるオランダ。なぜそんなに強いのか?という記事があったので超訳しました。
参考記事:Cycling News | Dutch Dominance: What Makes the Netherlands so successful?
そもそも自転車大国である
一人あたりの自転車保有数が世界一と言われるオランダ。オランダでは通勤でも当たり前のように自転車が使われ、そのうちの55%が女性だというのですから、女性サイクリストが変に思われることなんてないのです。自転車なんて男のやることだ、なんていう愚問がまかり通ることはありません。ツール・ド・フランスの地と比べても、その差は歴然のようです。
通勤や買い物で自転車で走ってる女性のハンドルさばきはとても素晴らしい。安定してる。フランスだったら危なっかしくてしょうがない。
(Marion Clignet、フランスの元プロ女子選手)
自転車クラブがたくさんあり、幼少期からレースに慣れ親しんでいる
そんな自転車大国オランダには、当然のことながらクラブも沢山あります。
今、トッププロの世界にいる彼女達は幼い頃からクラブでトレーニングを始めていた。両親やコーチなど、ボランティア的にサポートしてくれる人のおかげで、安全で楽しくレースに臨める雰囲気の中にいたはずなんだ。
(Thorwald Veneberg、オランダチームのマネージャー)
安全に、楽しく。これがないと続けようとは思いませんもんね。ミッチェルトンスコットのヘッドコーチ、ノルウェー出身のMartin Vestbyは自国と比較したオランダの環境をこう語ります。
オランダには、幼少期の頃から自転車に慣れ親しむためのクラブがたくさんある。大きなクラブだと、サイクリスト専用の1.5〜3kmのコースがあったりする。小さい頃はそこでクリテリウムレースをして、集団走行を学んでいくんだ。他の国だと小さい頃から公道に出さなきゃいけなくて、当然そんな中で安心してトレーニングなんてできない。
(Martin Vestby, ミッチェルトンスコットのHead Sports Director)
専用のコース!こうした環境の整ったクラブには男女問わず子供が沢山所属していて、仲間として長い間お互いを高めあえるのです。日本の自転車クラブや部活だと、女性部員が一人とか二人ってよくあること。もしその子が皆でわいわいするのが好きなタイプだったら「もっと楽しいことがしたい」と他の人気スポーツに移り気してしまうのは自然なことでしょう。人気があるスポーツは強くなる、という至極あたりまえのことなのです。
そして、沢山の女子サイクリストがいるということは、レースがたくさんできるということでもあります。オランダには、8歳から15歳までの子供向けステージレースなんかもあって、22カ国から800人の子供達が集まります。男女混合で、男子10歳の部と女子11歳の部が一緒に走るんだそうです。
才能ある選手を育成するインフラが整っている
そもそもオランダは自由と平等という概念にすごく敏感な国。それが何を示すかといえば、女性スポーツというモデル・その育成インフラが成熟しているということです。自転車競技で言えば、オランダには5つの女子プロチームがあります。メンバーは必ずしもオランダ人ばかりとは限りませんが、地元のオランダ選手にとって、他の国の選手よりは有利だということは間違いないでしょう。
さらに、オランダの自転車競技連盟は才能がありそうな若手をトレーニング・キャンプに送り込むシステムがあります。連盟のお金を使って。普通のことであるように思われるかもしれませんが、現実は厳しく、世界的に見ても女子サイクリング界では普通じゃないんだそうです。イギリスですら、ロンドン五輪の一年前、2011年の世界選手権前に計画されていた女子チームの合宿がおじゃんになったという逸話もあります。
このように男女平等が結果として現れているスポーツは決して自転車だけじゃありません。スケート、フットボール、ホッケー、オランダの女性陣が最強を誇る競技はたくさんあります。直近の平昌オリンピックでもオランダが獲得した8個の金メダルのうち5個が、全てのメダル20個のうち12個が女子選手によるメダルです(ちなみに全てスケート)。
ライバルが沢山いる
国内にいる沢山のライバルの存在は、全てを有利にさせます。「切磋琢磨」という言葉が正しいのでしょうか。簡単に国の代表になれてしまう選手と、国内で厳しい競争に勝ち抜いたオランダ選手のレベルが違ってくるのは当然です。ライバルがたくさんいることで、オランダのプロチームは生まれたという逸話も。1990年代のライバル関係が、未来の若者たちに新しい道を切り開いたのです。
1990年代のこと。Van MoorselとMonique Knollという2人の選手とのライバル関係の果てに、Knollはナショナルチームを離れて自分のチームを作るという決断をした。そのときにKnollにスポンサーがついた。これがオランダの女性プロ自転車選手の先駆けとなった。
(Rene Koppert、元プロ・Duth Cyclist of the Year Awardの運営者)
ロールモデルがいる
〇〇みたいになるんだ!というわかりやすい目標は、子供にとってはとても大事です。その点、オランダには目指すべきスター選手に事欠きません。昨年のジュニア世界選手権TTで優勝したRozemarijn Ammerlaanが乗っていたバイク(上写真)は、エリート女子優勝者のVan Der Breggenが昔乗っていたバイク。
私のバイクは昔彼女がラボバンクの育成チーム時代にいたころ乗っていたバイク。チームがこのバイクを売ると言ってたから迷わず買ったわ。彼女の名前入り!クールでしょ。
(Rozemarijn Ammerlaan、ジュニア世界選手権TT優勝者)
まさに最強の系譜。ちなみに、オランダにはKeetie van Oosten-Hage Trophyという名前の賞があります。一年でもっとも活躍したオランダ女性選手に送られる賞。昔は年間最優秀選手賞というとオランダ全体で一人の男子選手にしか与えられていなかったのですが、連盟はその賞をKettie van Oosten-Hageに贈りたいと思い、新しく賞をつくりました。役員たちは「最優秀選手賞は男子選手に贈るものだ」とごねたそうですが、他のメンバーが「そんなら新しいの作ったる!」という感じで作ったそうで、それからずっとこの賞の授与は続けられています。
女子プロとしての文化が成熟している
オランダチームのプロフェッショナリズムを表す、強すぎるゆえのエピソードを一つ。
彼女たちはコミュニケーションを大事にする。心の片隅にしまってなんておかずに、とにかく話す。皆が皆こういう。私は勝ちたい。でも、もっと大事なことは、私達の誰かが勝つということ。最悪なのはオレンジの選手(オランダのチームカラー)同士が争ってるということで、みんなそれが大嫌いなんだ。最大のゴールは、オレンジの選手が勝つということ。
(Thorwald Veneberg、オランダチームのマネージャー)
自分のエゴだけじゃなくて、結果にこだわる。その姿勢がプロフェッショナリズムだと感じずにはいられません。さらにマネージャーは続けます。
彼女らはすごく熱心に自分たちが思っていることを話す。それは時にとても難しいことだけど、それでもクリアに自分の思いの丈を話そうとする。
(Thorwald Veneberg、オランダチームのマネージャー)
日本人が苦手とされていることでもあると思いますが、一流のアスリートは日本人でも自分の思いをはっきり語る人が多い気がします。他国のライバル選手もオランダ選手のマインドを絶賛。1984年、第一回の女性版ツール・ド・フランスを制したアメリカ人、マリアン・マルティンはこう語ります。
彼女らは素晴らしいスポーツ選手だった。常に「おめでとう」とか「良いレースだった」と言っていた。
(Marianne Martin, 第一回女性版ツール・ド・フランス優勝者)
そして、フランス人選手からみても。
他の国の選手と比べて、オランダの選手たちはみんなナイスな子たちだった。わたしたちはフィニッシュラインを目指して必死で争う間柄なのに、レースが終わったあとは違った関係になるの。最初は少し変に感じたけど、彼女らとは友達にもなれるしライバルにもなれる。オランダの教育のおかげなんじゃないかな。
彼女たちのチームには、スプリンターもクライマーも、リードアウトの選手もいた。女子レースではとてもめずらしいことなの。とても組織だっていて、レース前のミーティングやレース後のデブリーフもしていた。プロフェッショナルな意識を感じた。彼女たちは”チーム”としてレースをして、チームとしてリーダーをアシストしていた。それは間違いなく敬意にあたるものだった。
(Marion Clignet、フランスの元プロ選手)
マネージャーからみても然りです。
彼女たちのレース、トレーニング、生活を見てほしい。全てを賭けているのが分かると思う。それが彼女らにとってアドバンテージになるんだ。
(Thorwald Veneberg、オランダチームのマネージャー)
全てを賭けている。原文では、ALL OR NOTHING(全てか、さもなくば無か)と言う言葉が使われています。この言葉の力強さに、プロとしての覚悟を感じずにはいられません。
なぜ他の国は成功しないのか
隣の自転車大国ベルギーですら、オランダからは大きく遅れを取っていると言います。理由は、まだ「女子レース」というものが正当に評価されていないから。
過去5年で変わり始めてはいるけれど、まだ男の世界であることに変わりはない。一般的に、女子レースは見下されているフシがある。
(Martin Vestby, ミッチェルトンスコットのHead Sports Director)
スカンジナビア半島の国々では、そもそも自転車自体がメジャーな競技ではありません。フランスではどうなのかClignetにも聞いてみましょう。
フランスは世界最大の自転車イベントが開催されているのに、女子にはほとんど何もしてくれない。連盟のマインドセットにまず問題がある。女性のVice precidentを指名したのだって最近になってからだし、”féminisation du vélo(サイクリングの女性化)”というイニシアチブを立ち上げようかと検討していて、そのワードチョイスが私をいらだたせる。意味がわからない。
(Marion Clignet、フランスの元プロ女子選手)
1970-80年代に米国で育ち、女性のサイクリングのブームを経験し、初回の女性版ツール・ド・フランスをティーン・エイジャーとして見ていたClignetは女性の自転車競技の存在を疑問に思ったことすらありませんでした。しかし、その女性版ツール・ド・フランスは今はもう行われていません。フランスの自転車競技界に、Clignetはこう苦言を呈します。
フランスの自転車連盟は、オランダに行って彼らがなにをしているのか見て学んでほしい。でもフランス人は他人から学ぶ必要なんてないと考えてるから、たぶん学ぶなんてことはないだろうけど。
(Marion Clignet、フランスの元プロ女子選手)
「オランダ選手は風に強い」は迷信?
ちょっと話がずれますが、「オランダ選手は風に強い」という話を聞いたことないでしょうか?オランダ選手は風に強い。スペイン選手は山に強い。イギリス選手はTTに強い…これらはすべて、言い訳に過ぎないとミッチェルトンスコット女子チームのヘッドコーチは言います。
確かに、今までどんなレースをしてきたかは選手の能力に影響を与える。オランダには風の強くてエシュロンが形成されるレースが多い。でも結局は、選手一人一人の能力をどうやって伸ばしていけたが問題になる。もしある選手が強風レースが苦手でも、他のところで才能を見出して育成させてあげればいい。 それに、Annemiek van Vleutenは確かにエシュロンとクリテリウムで成長してきたが、上りでも驚くほどの力を発揮しているだろう?
(Martin Vestby, ミッチェルトンスコットのHead Sports Director)
なるほど、他の才能を伸ばすのですね。それから天才には生まれた国も何も関係ないと。Koppertも同様に、オランダ流の戦い方なんてものはないと主張しながら、最強オランダ軍団の中でも不動の女王の一時代を築いたMarianne Vosを、プロフェッショナルな戦術を女子レースに持ち込んだ最初の選手だと称賛します。
フォスの戦術的な走り方は、女子サイクリング界を大きく変えた。言い方は正しくないかもしれないが男子のように戦術的な走り方をした先駆けの選手なんだ。一方、最近の男子レースは結果が予測できてしまってつまらないものも多い。でも女子レースはもっと面白い。アタックの数が多いんだ。
(Rene Koppert、元プロ・Duth Cyclist of the Year Awardの運営者)
女子レース、面白いんですね。良いことを聞きました。全然見てないので、今度見てみたいと思います。フランスからもオランダ選手への畏敬の念が。
オランダ選手は戦術的なビジョンを持っている。生まれつきなものかもしれないが、彼女達には恐れもない。いつアタックすべきかも分かっている。それはすべて、大きなアドバンテージだ。
(Marion Clignet、フランスの元プロ女子選手)
オランダ最強時代は、まだまだ終わりそうにありません。
ー□